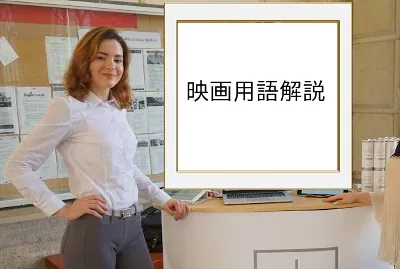映画法は映画を規制する法律
映画法は、日中戦争から第二次世界大戦にかけての戦時体制下で施行された法律で、映画の全面的な国家統制がその目的でした。
当時の内務省と文部省が、ドイツやイタリアの映画国策法を参考にして法案を作成しました。
この法律は全26条からなり、第1条では「本法ハ国民文化ノ進展ニ資スル為映画ノ質的向上ヲ促シ映画事業ノ健全ナル発達ヲ図ルコトヲ目的トス」と掲げられています。
しかし実際には、映画製作や配給の許可制、従事者の登録制度、脚本の事前審査や完成フィルムの検閲、外国映画の制限、優良映画の選奨、文化映画やニュース映画の強制上映、興行の規制などを含む国家統制が行われました。
映画法はいつ公布されましたか?
映画法は、1939年4月5日に公布、同年10月1日に施行されました。
この映画法は、第2次世界大戦後の1945年12月26日に廃止され、その後しばらくはGHQが映画統制を担当することとなりました。
功罪両面での評価が必要
映画法以前には、日本映画の改善・改良を目的として1934年に映画統制委員会が発足するなど、映画統制は保護助成と並行して進められる傾向がありました。
このため映画法も「日本初の文化立法」とされ、映画業界の健全化や安定化を歓迎する声もあったようです。
映画法による第一回文部大臣賞では、戦争映画『土と兵隊』のほか、ヒューマンドラマ『土』や芸道もの『残菊物語』が選ばれ、文化映画やニュース映画も大きく発展しました。
また、フィルム・ライブラリーを活用した保護育成策も打ち出されるなど、映画法については功罪両面での評価が必要とされています。
→映画用語集へ戻る