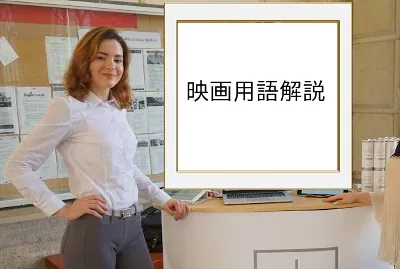映画倫理機構について
映倫(映画倫理機構)は、「表現の自由を護り、青少年の健全な育成を目的として、映画界が自主的に設立した第三者機関」(映倫Webサイトより引用)です。
映倫は、映画鑑賞のための年齢制限の規定を設け、劇場用映画・予告篇・ポスターなどの審査を行ない、「G」から「R18+」までの制限区分を与えます。
映倫の前身となる映画倫理規程管理委員会(旧映倫)は、1949年に発足し、これをもとに1956年に映画倫理管理委員会(新映倫)が設立され、現行の組織の基礎が築かれました。2009年に「映画倫理委員会」と改称、2017年に一般財団法人映画倫理機構となっています。
映倫の歴史
映画倫理規程管理委員会(旧映倫)
戦前・戦中の映画統制は「映画法」に基づいて行われていましたが、戦後の1945年9月より占領軍のGHQ(連合軍総司令部)が映画政策も担うことになり、その内部組織によって日本映画の検閲も行われることになりました。
GHQによる管理体制は1952年まで続きましたが、映画検閲はそれ以前の1949年に終了し、代わって映画業界による自主的な審査機関を設置することが求められました。
これを受けて日本映画連合会は、アメリカの「プロダクション・コード」を参考に映画倫理規程を制定し、その運営のために同年、映画倫理規程管理委員会(旧映倫)を発足させました。
以後、映倫の審査を受けた作品にはタイトル画に審査番号が付されるようになります。第一号は『大都会の丑時』(1949年)でした。
旧映倫は、業界関係者が委員を務め、内部機関として運営されており、法的権力はありませんでした。
当初、アメリカ映画業界は、すでに本国のプロダクション・コードを通過した作品であるとして、旧映倫の審査に非協力的でした。ですが、『暴力教室』(1955年)の公開時に日米の審査基準の違いが問題となり、それ以降は協力するようになっています。
映画管理委員会(新映倫)
1956年に「太陽族映画」がブームとなったときに、マスコミや一般の間からその審査基準に疑問が呈され、文部省による検閲法の制定や警視庁による映倫設立案も提示されました。
このような動きから業界の自主性・自立性を守るため、映倫の組織改編が行われ、委員は外部有識者に委嘱され、運営も業界から切り離されました。
こうして、1956年12月に「映画倫理管理委員会」が設立され、現在の映倫の組織に改編されました。
現在の映倫
2009年には、映画倫理規程が内外の環境変化に応じた映画倫理綱領に改編され、機関名も「映画倫理委員会」に改称されました。
2017年、任意団体としての映画倫理委員会は解散し、同年4月1日から新たに設立された一般財団法人「映画倫理機構」に業務を移管しました。
審査は同機構内に新たに設けられた「映画倫理委員会」が引き続き行っています。
現在は、5名の映倫委員のもと、8名の審査員が有料で審査を行い、その審査料によって運営費が賄われています。
なお、全国興行生活衛生同業組合連合会(全興連)に加盟している劇場では、映倫審査を受けていない映画は上映されません。
→映画用語集へ戻る