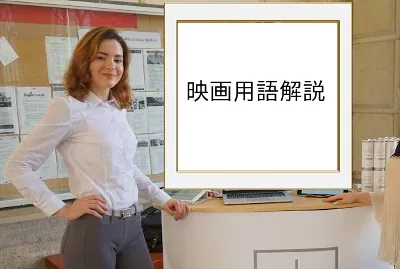映画用フィルムの誕生
映画用フィルムは、もともと写真用に開発されたフィルムを転用したものです。
1889年、アメリカのジョージ・イーストマンがセルロイドをベースにしたロールフィルムを完成させました。
その後、エジソン研究所がこれを改良し、撮影用カメラの開発に合わせて35ミリ幅のフィルムが採用されました。そして1891年にはキネトスコープの特許を取得します。
一方、イーストマン社では工場で42インチ幅の原盤フィルムを15本に裁断し、70ミリ幅のロールフィルムを製造しました。この70ミリフィルムを半分に裁断した35ミリ幅のフィルムがエジソン社に提供されました。
映画用フィルムの規格
世界で最初の映画を上映した、フランスのリュミエール兄弟もキネトスコープを見てこのフィルムを採用しています。
1905年には映画製作者国際会議で35ミリ幅が標準規格として認定されました。
以降、映画用フィルムの基本はこの35ミリ幅となり、他にも70ミリ(撮影用は65ミリ)や小型映画用の16ミリ、8ミリなどが一般的に使われています。
映画用フィルムの呼び方
映画用フィルムは、使用される段階ごとに異なる名称で呼ばれます。以下は一般的な映画製作の過程におけるフィルムの呼称です。
ネガ
まず、撮影後に現像されたフィルムは、明暗や色調が反転(カラーの場合は補色関係)して記録されており、これを「ネガ」と呼びます。
ボジ
次に、ネガを映写に適した映像に戻したものが「ポジ」です。
プリント
上映用に複製されたフィルム(完成版の映画)は「プリント」と呼ばれます。
デュープ
また、オリジナルフィルムを保護するため、複製専用に原版をコピーすることがあり、これを「デュープ」といいます。
映画製作の基本的な順序
基本的な製作工程は、オリジナル・ネガ→マスター・ポジ→プリント用デュープ・ネガ→映写用ポジ・プリントという順序で行われます。
デジタル技術の発展と映画用フィルム
上で紹介した工程では、撮影フィルムから何回にもわたって複製が行われるため、画質の劣化は避けられませんでした。
しかし、デジタル技術が発展したことで、撮影フィルムの映像をデジタル変換して作業することが可能になり、複製による画質の劣化は大幅に軽減されました。
現在では、撮影から仕上げまで全てデジタル工程で行い、フィルムを一切使用しない映画も増えています。
→映画用語集へ戻る